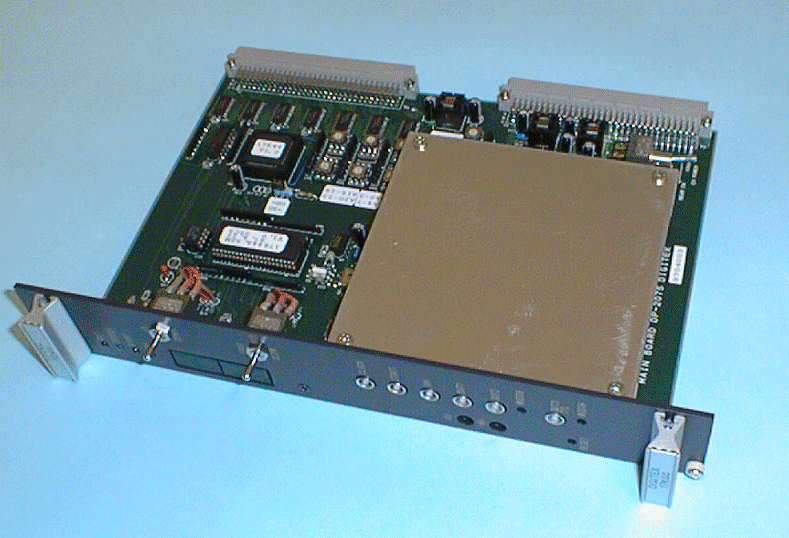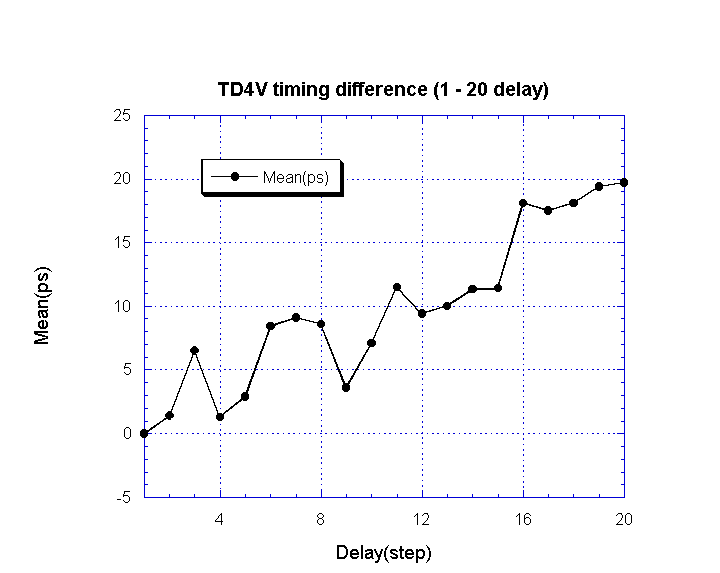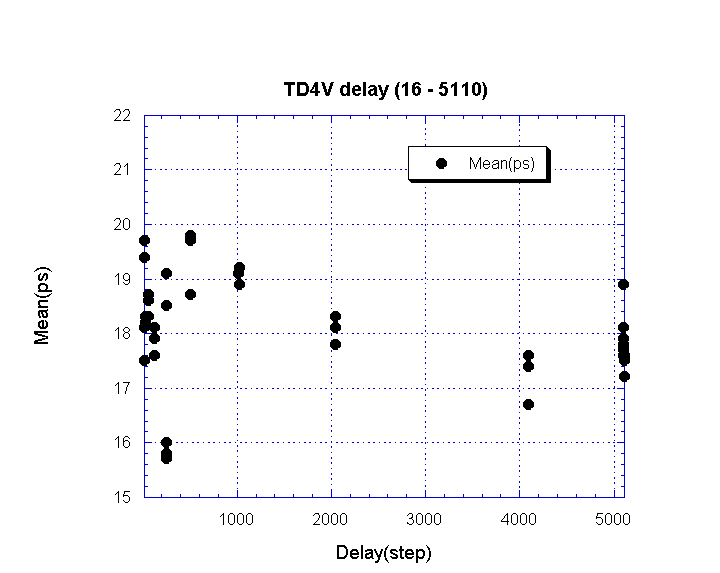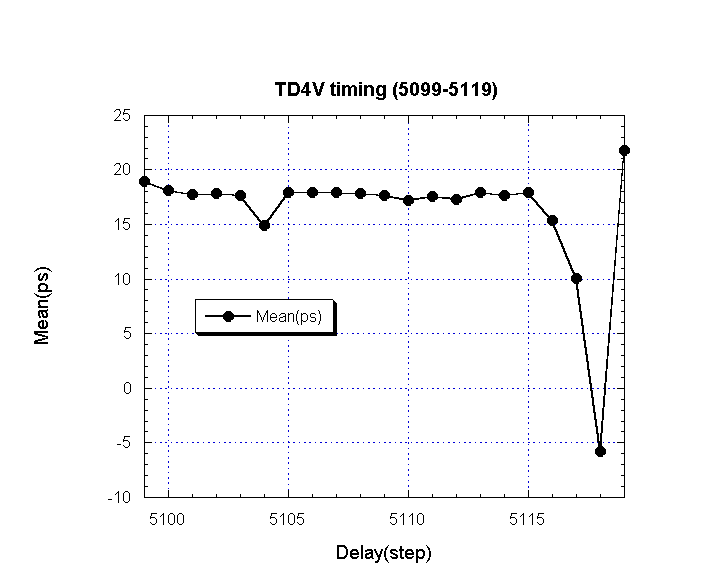- 1-1 Inhibit入力(NIM)
入力ありで INHランプ点灯、Output消灯、出力disable
入力なしで INHランプ消灯、Output点灯、出力enable
- 1-2 VMEからのinhibit(IObase+4)
設定1(inhibit) INHランプ変化なし、Output消灯、出力disable
設定0(enable)INHランプ変化なし、Output点灯、出力enablle
スタート信号を508.887MHzの1/5120とすると、1から5119まで出力
0および5120は出力なし
5120以上は不定
- 3-1 NIM出力 最小幅 :2.5ns
最大幅 :130ns
fall time :700ps
rise time :800ps
- 3-2 TTL出力 最小幅 :11.5ns
最大幅 :286ns
rise time :5.8ns
fall time :3.6ns
- 4-1 RF入力とジッターの関係
遅延の設定値は1111に固定した。TD4VのNIM出力をトリガーとし、RFの508.887MHzを HP54121Tサンプリングスコープを使い観測する。RFのゼロクロス点の時間方向の広がりをHistogram機能で積算し、平均、標準偏差を求める。
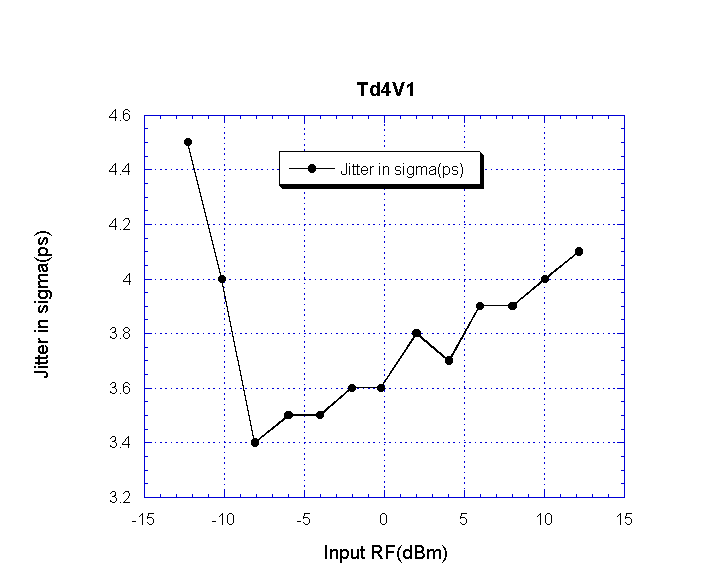
最低-12.28dBmから動作し始め、10dBmを超えた値でも動作している。ジッターの絶対値としては一番大きな4.5ps程度であってもTD2の代表値12ps、TD4(original)の5ps程度より遙かに良い。それらの内でも、-5dBm程度の場所が一番良好であり、RF入力を上げていくに従って徐々に悪化する。
- 4-2 遅延値と位相の関係
4-1と同様にゼロクロス点の絶対位相のずれを観察する。回路的にはcounterの後段にD-FFが入ってRFでラッチされているので、counterでの遅延時間のずれはここで吸収されているはずである。入力RFは-5dBmに固定した。スタート信号は1/5120信号である。明らかにdelay設定値によって変動している。特にdelay値の端(0に近いあたりと5120に近いあたり)の変動が大きく、約20ps以上にも達している。その中間では全幅でおおむね4ps程度に収まっている。これ自身は大変優秀であるとは思うが、delayによって変動する理由がわからない。可能性として、508MHzのラッチとcounter outputのタイミングが近すぎ、ほとんど素通りさせてしまっているのではないかと思われる。counter outputとlatchのタイミングをnominalに1ns程度ずらしてしまえばどうだろうか。
参考のために、TD2とTD4(オリジナル)の測定結果を示す。
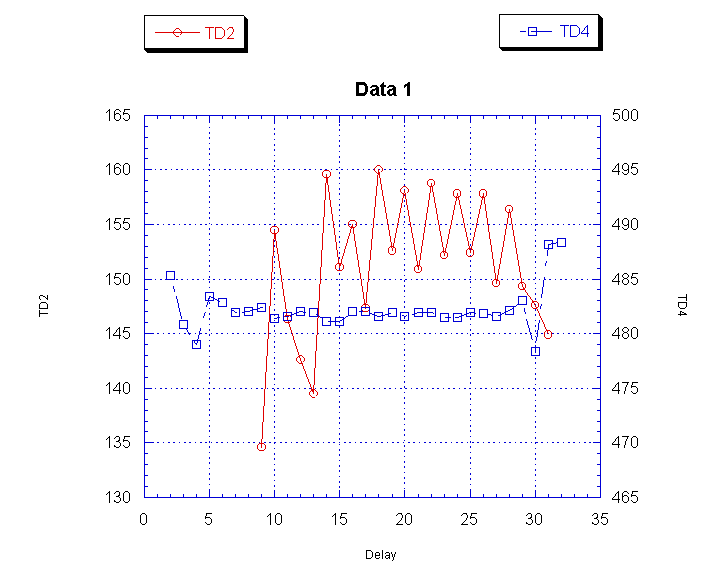
TD2の変動は遙かに大きく、隣のdelay値の間でnominalに7ps程度は変動する。またこのデータには出ていないが、1nsもずれてしまうことがある。
TD4(orig)はそれに比べるとおとなしいが、delay値が大きく変わるときにやはり10ps程度は変動している。
TD4-V使用説明書へのリンク
Makoto Tobiyama 7/May/97